「子供は40000回質問する」の書評

モンテッソーリ教育やレッジョエミリア教育などのオルタナティブ教育では,子供自身が興味を持っていることに取り組むことが大切と言われています.つまり,子供が好奇心を持っていることであれば,自主性や主体性を発揮できるという教育手法です.
その中で,好奇心とは何か,どうすれば好奇心を持つことができるのか,など「好奇心」について知りたいと思うようになりました.そこで,「子供は40000回質問する」を読みましたので,感想などをご紹介いたします.
子供に限らず,好奇心について広く学ぶことができる最高の1冊!
2023年に読んだ本の中で,TOP3に入る名著です!
子供は40000回質問する
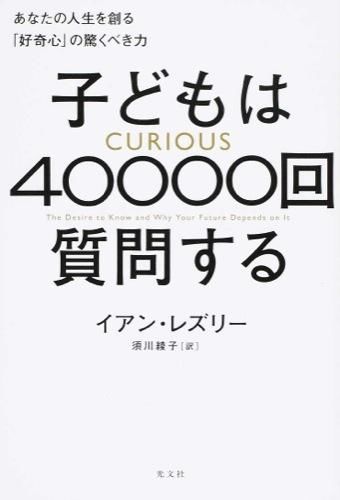
著者:イアン・レズリー
訳者:須川綾子
発行:光文社
サイズ:文庫判
ページ数:400ページ
初版:2022年5月11日(文庫版)
本書の概要
本書では,「好奇心のはたらき」,「好奇心格差」,「好奇心を持ち続けるためには」などを学ぶことができます.本書の内容は,科学論文に基づいた信頼できる情報です.著者個人の見解が語られているものではありません.
タイトルには,「子供」とありますが,子供に限らずに「好奇心」全般に関する内容です.タイトルとなっている「子供は40000回質問する」は,実際に2才~5才の間に4万回質問すると言われています.
「学業成績と関連性の高い能力」,「独創的なアイデアに必要なもの」,「知識を暗記する必要性」,「魅力的なストーリーの共通点」,など興味深いテーマが多く取り上げられています.
著者:イアン・レズリー
ノンフィクション作家.著書に「CONFLICTED」などがある.
本書の感想

「好奇心」について学ぶことができる最高の1冊!私が2023年1月~4月に読んだ本の中でもTOP3に入る名著です.本当に学びが多かったです.
大人にとっては,「好奇心格差」の内容が勉強になります.つまり,好奇心を持っている人と持っていない人の間に格差が生じており,今後,さらにその格差が拡大するだろうということです.
好奇心を持っている人は,新しい知識や技術に対応することを好みます.近年は,テクノロジーの進歩が速く,どんどん新たな知識や技術が必要になります.そのため,社会・企業からは,テクノロジーの発展に伴って「成長できる人材」が求められています.そして,成長できる人材とは,好奇心を持っている人だと著者は述べています.
私も,著者の考えに同意します.好奇心を持っている人は,常にアンテナを張っていて,面白いこと・便利なことをいち早く試してみる人が多い印象です.逆に,好奇心が少ない人は,非効率な従来のやり方にこだわっている印象です.
本書は,「すぐに使えるテクニック系」の浅い本ではありません.その分「好奇心」というものの本質について,深く掘り下げて学ぶことができます.
こんな人におすすめ!
- 子供の好奇心を育てたい人
- 好奇心を持ち続けることの重要性を知りたい人
- 好奇心を持ち続ける方法を知りたい人
- 教育に関わる仕事をしている人
以上,参考になれば嬉しいです.







